キックオフ時のフォーメーションとスタメン配置
京都サンガは試合開始時、4-1-2-3の布陣(4-3-3に近い形)で臨みました
スターティングメンバーの配置は以下の通りです
- GK: 太田岳志(背番号26)
- 最終ライン(4バック): 右SBに須貝英大(22番)、
右CBに宮本優太(24番)、左CBに鈴木義宜(50番)、左SBに佐藤響(44番) - 中盤: アンカー(1ボランチ)に川﨑颯太(7番)、
インサイドハーフに福岡慎平(10番)と平戸太貴(39番) - 前線3トップ: センターフォワードにラファエル・エリアス(9番)、
右ウイングに松田天馬(18番)、左ウイングに原大智(14番)
この配置により、中盤では川﨑が単独で守備の底を支え、
平戸と福岡がやや前目で攻守にリンクマンの役割を担いました。
前線はエリアスを最前線のターゲットに、原と松田が両翼からサポートする形です。
守備時には両ウイングの原と松田が中盤に下がって4-1-4-1または4-4-2気味のブロックを作り、
川﨑を中心に中盤を厚くする狙いが見られました。
攻撃時には逆に、川﨑がアンカーとして最終ライン前に残り、
両SBの須貝・佐藤が高い位置に押し出して幅を取り、
2列目の平戸・福岡は前線に絡んで厚みのある攻撃を仕掛けています
(守備重視の横浜FCを**「攻撃の大波」で崩す**狙いsanga-fc.jp)。
特に両サイドバックは積極的で、右SB須貝は押し上げてクロス供給を狙い、
左SB佐藤も機を見てオーバーラップやロングフィードを試みました。
前半:序盤の展開と先制点の戦術
試合序盤、京都は前線からプレスをかけつつも、
ボール保持時にはシンプルなロングボールと素早い連携で相手守備を崩そうとしました。
その狙いは開始早々に的中します。
前半15分、京都が先制ゴールを奪いました
この場面では京都のゴールキックから原大智が空中戦で競り勝ってボールを頭でそらし、
右サイドに流れたエリアスがそのボールを収めました。
エリアスはワンタッチで中央の川﨑へ落とし、
川﨑も素早くワンタッチで前線に縦パスをつなぎます。
ペナルティエリア手前右側で受けた松田がワンタッチで原に落とし直し、
最後は原がペナルティアーク付近から左足を一閃してゴール右隅に突き刺しました
このゴールは、ターゲット役の原を起点とした縦に早い崩しで生まれており、
京都の狙い通りに前線の高さと連携を活かした形と言えます。
先制後、京都は引き続き集中した守備と効率的な攻撃を見せます。
前線の原とエリアスは相手3バックに対して積極的にプレスをかけ、
後ろの川﨑も前に出て横浜FCのボランチ(ユーリ・ララ)にプレッシャーを与えました。
横浜FCも反撃に出て前線のルキアンを起点に何度かゴールに迫りましたが、
京都の守備陣は4バックと川﨑を中心に粘り強く対応します。
特に両CBの宮本と鈴木はルキアンへの縦パスを跳ね返し、
川﨑がこぼれ球を回収する動きでセカンドボールを支配しました。
攻撃面では、京都はボールを奪ってから素早く縦に展開し、
追加点の機会をうかがいます。
前半37分には、左SB佐藤が自陣寄りの中盤左サイドから思い切ったロングスルーパスを通し、
裏へ抜け出した松田がゴール左で左足のダイレクトシュートを
放つシーンがありました
これは相手の背後のスペースを突いた形でしたが、
シュートは相手GK市川の好セーブに阻まれ追加点とはなりませんでした
この場面でも佐藤の高い位置取りと精度あるフィード、
松田の果敢な飛び出しが光っており、
京都が狙う素早いトランジションからのチャンス創出が表れています。
前半は京都が1-0とリードし、
プレスと速攻を武器に主導権を握ったまま終了しました。
ハーフタイムの戦術調整:4-3-3からダイヤモンド型へ
京都はリードを保ったまま迎えたハーフタイムに、最初の交代策を講じました。
松田天馬に代えてMFのジョアン・ペドロ(6番)を投入し、
中盤を厚くする策を取ります(後半開始時の交代)。
この交代によって前線の布陣を若干変更し、
フォーメーションは4-3-3から4-4-2(中盤ダイヤモンド型)気味へとシフトしました。
- 前線は原とエリアスの2トップとなり、原大智がやや左寄りのストライカー、
エリアスがやや右寄りorセカンドストライカー気味に配置されました
(2トップで最終ラインにプレッシャーを継続)。 - 中盤はダイヤ型を形成。アンカーに川﨑颯太、ボランチ脇にジョアン・ペドロと福岡慎平が並び、トップ下的な位置に平戸太貴が入る形です。
平戸が2トップの背後でリンクマン兼プレスの起点となり、
川﨑とジョアン・ペドロで守備のブロック中央を固める狙いでした。
このシステム変更は、前半に横浜FCが中盤で数的優位を作ろうと
していたことへの対策とも考えられます。
京都は中盤センターを3枚から4枚に増やすことで、
横浜FCのボール保持に対抗し、リードを守り抜く構えを強めました。
一方で松田を下げたことでサイドの攻撃力は一人減りますが、
平戸がトップ下に入ったことで中央からの崩しやセカンドボール回収に厚みを持たせています。
また原とエリアスの2トップは前線でボールを収めつつ、
横浜FCの3バックに対して数的同数でプレスをかけられるため、
前線からの守備も継続できるメリットがあります。
後半立ち上がり:同点ゴールを許す展開
しかし、このハーフタイムの調整にもかかわらず、
後半立ち上がりに横浜FCに同点弾を許してしまいます(後半4分=通算49分)。
後半開始から横浜FCが前への圧力を強め、
京都は自陣深く押し込まれる時間帯となりました
後半5分、横浜FCは左センターバックの福森晃斗が
左サイド高い位置からアーリークロスを供給します。
京都守備陣は4バック+中盤でゴール前を固めていましたが、
このクロスに対しファーサイド(右サイド)の背後を突かれ、
横浜FCの山根永遠にファー側でヘディングで折り返されました。
最後はゴール前に飛び込んだFWルキアンに右足で押し込まれ、
京都は失点を喫しました
この場面では、京都の弱点となりうる両サイドの背後を突かれています。
ダイヤモンド型の中盤にしたことでサイドの守備はSB任せになりやすく、
また横浜FCは後半開始からウイングバックの位置を高めてきました。
福森(横浜FC)が思い切って攻め上がったことで須貝と
右CB宮本の間のスペースを使われ、
さらに反対サイドの佐藤と左CB鈴木の裏にも山根が侵入する形となりました。
京都は中央を厚くした反面、
横浜FCのワイド攻撃への対応が後手になってしまい、
早い時間帯で1-1の同点とされています。
同点に追いつかれた直後、京都ベンチは素早く攻撃的な修正策を取りました。
後半11分(56分)に福岡慎平を下げ、奥川雅也(29番)を投入します
この交代の意図は明確で、再び前線に推進力と幅を与えることでした。
同点となり守りに入る状況ではなくなったため、
京都は中盤の一枚(福岡)を削ってでも攻撃的な選手を投入し、
勝ち越しゴールを狙いにいきます。
後半:奥川投入による攻撃活性化と勝ち越しゴール
奥川雅也の投入により、京都は再び前線の枚数を増やし
フォーメーションを再調整しました。
明確な形としては
4-2-3-1または4-3-3に再シフトした形に近い動きになっています。
川﨑颯太とジョアン・ペドロのダブルボランチで中盤の底を支え、
その前方に平戸(後に平戸と代わった奥川がトップ下的に振る舞う)という構成です。
一方、奥川は攻撃時には主に左サイドにポジションを取り、
原大智は再び中央寄りのFWの位置取りに戻りました
(原とエリアスの2トップ気味から、
原1トップ・奥川左WG・エリアス右WGのような前線3枚に近い形へ移行)。
守備時には奥川も中盤に戻り、
実質的には4-4-2のように原とエリアスの2トップでプレスをかけ、
奥川と平戸が両サイドハーフ的に相手WBをケアする形で対応します。
このようにして同点直後から再び攻撃的な布陣を整え、
勝ち越し点を奪う狙いを明確にしました。
奥川の投入効果は大きく、京都の攻撃に推進力と変化をもたらします。
奥川はボールを持てるアタッカーであり、左サイドでボールを受けて仕掛けたり、中にカットインしてチャンスメイクする動きを見せました。
また彼の投入によって前線の原・エリアス・奥川という実質3トップの形が復活し、
横浜FC守備陣に再び圧力をかけ始めます。
そして迎えた後半25分(70分)、京都が待望の勝ち越しゴールを奪います。
このシーンでは再度シンプルかつ効果的な形でゴールをこじ開けました
右サイド深い位置でボールを持った須貝英大(右SB)が、
ゴール前へロングボール気味の高精度なクロスを送り込みます
狙い通りペナルティエリア中央付近で
原大智がDFと競り合いながら高い打点でヘディングで落とし、
ボールはゴール正面やや右寄りのスペースへ。
そこに走りこんだのが投入直後から前線に絡んでいた奥川雅也でした。
奥川は胸トラップでボールを収めると素早く切り返し、
マークについていた相手DF(福森晃斗)をかわして左足を振り抜きます。
シュートは相手GKの逆を突き、
ゴール右隅に冷静に流し込まれました
このゴールは京都の攻撃パターンを体現したものです。
ターゲットマンの原がまたしても空中戦で起点となり、
サイドからの早いクロスに対してセカンドボールを味方が
回収してフィニッシュまで持ち込む形でした。
須貝のクロスの判断と質、原のポストプレー、
奥川の決定力と個人技が見事にかみ合い、
采配面でも56分の奥川投入がずばり的中した格好です
これでスコアは2-1となり、再びリードを奪った京都は残り20分強を戦うことになります。
終盤:リード後の戦術変更と5バックでの逃げ切り
勝ち越しに成功した京都は、残り時間でこの1点リードを守りきるための戦術にシフトしていきます。
まず後半26分(71分)には3度目の交代カードを使用し、
平戸太貴に代えて米本拓司(8番)を投入しました
米本は守備的MFであり、この投入によって中盤の守備力をさらに高めています。
川﨑とジョアン・ペドロに加え米本が入ることで、
中盤は実質アンカー+ダブルボランチの3枚(トリプルボランチ)のような布陣になりました。
これにより京都は4-3-2-1に近い非常に守備寄りの陣形に変化します。
最前線には原大智を残し、奥川雅也とエリアスは少し下がって中盤の両脇
(シャドーないしサイドハーフ)の位置までリトリート。
中盤中央は川﨑・ジョアン・米本の3人が横並び気味 or 川﨑を中央に据えた
トリアングルでブロックを構築し、
最後方の最終ライン4人と合わせて計7人が自陣に厚い壁を作る形です。
攻撃時には原を起点に奥川がカウンターに出る形を残しつつも、
基本的には4-5-1の守備ブロックで横浜FCの攻撃を受け止めに入りました。
横浜FCも同点を目指して選手交代を重ね、京都陣内への攻勢を強めます。
京都は自陣に人数をかけて対応し、
中盤でボールを奪っても無理に攻めず前線の原にロングボールを当てて時間を作るなど、
ゲームコントロール重視の戦い方に切り替えました。
原大智は前線で体を張ってロングボールを収め、
ファウルを誘ったりスローインを得るなど時間を稼ぐプレーでチームに貢献します。
また奥川も守備に戻って中盤の左サイドをケアし、
エリアスも運動量を落とさず前線と中盤を行き来していました。
そして試合終了間際、京都は最後の交代策で守備を固めます。
後半45分(90分), 残っていた交代枠で
ラファエル・エリアス(FW)と佐藤響(左SB)を下げ、
DFのパトリック・ウィリアム(4番)とDF福田心之助(2番)
を投入する同時交代を行いました
この大胆な2枚替えで一気に最終ラインの枚数を増やし、
布陣を5バック(5-4-1)に変更して逃げ切り態勢を固めます。
具体的には、従来の4バックにパトリックを加えて
3センターバック体制(宮本優太・鈴木義宜・パトリックの3CB)とし、
左右に須貝英大と福田心之助の両ウイングバックが並ぶ形です。
中盤は川﨑・米本・ジョアン・奥川の4人が横一線に近い形で並び、
最後尾に5人、その前に4人という5-4の強固なブロックで守りを固めました。
原大智はただ一人最前線に残り、
最終盤は実質的に守備専念の5-4-1です。
五列の壁を作ることで横浜FCにサイドの裏を取られてもカバー人数で上回り、
中央にも容易に侵入させない狙いです。
この終盤の布陣は功を奏し、
京都は横浜FCの猛攻を凌ぎ切りました。
横浜FCはロングボールやミドルシュートで何とかこじ開けようとしましたが、
京都は人数をかけた守備で体を張ります。
後半53分(98分)にはバイタルエリア手前から
横浜FCの小倉陽太に強烈なミドルシュートを打たれる場面がありましたが、
GK太田岳志が横っ飛びのファインセーブでこれを阻止し、
スタジアムを沸かせました
結局そのまま試合終了のホイッスルが鳴り、
京都サンガが2-1で勝利を収めています
京都サンガの戦術的狙いと評価
この試合の京都サンガは、相手の布陣や試合状況に応じて
フレキシブルにシステムを変化させる
高度なゲームマネジメントを見せました。
初期の4-1-2-3で挑んだ攻撃的布陣から始まり、
ハーフタイムで中盤を増やす4-4-2ダイヤモンド型への変更、さらに同点後には再び前線を厚くする布陣へのシフト、リード奪取後は徐々に守備固めの布陣へ移行し、
最終的には5バックで試合を締めるというように、
試合の流れに沿ってフォーメーションを柔軟に調整しました。
戦術的な狙いとして顕著だったのは、
攻守の切り替え(トランジション)の速さと前線の高さを活かしたダイレクトプレーです。
ビルドアップでは無理に後方から繋ぎ倒さず、
要所でロングボールを効果的に使っています。
1点目と2点目はいずれもロングフィード→ターゲットへの当て→周囲の素早いサポート
という形で生まれており、
これは明確に練習された形でしょう。
特に長身の原大智を起点とする戦術は
狙い通り機能しました。
原はこの試合、攻撃時はポストプレーと決定力で存在感を示し(先制点を奪取)、
守備時には前線からのファーストディフェンダーとして奮闘しました。
また、両ウイング(原、松田)や途中から入った奥川は、
攻撃時にはサイドから仕掛けつつ守備時には中盤まで戻ってブロックを形成し、
90分を通してハードワークしています。
川﨑颯太を中心とした中盤も、プレス時には前に出て相手ボランチにプレッシャーを与え、
守勢の際には最終ライン前にしっかり残って盾(スクリーン)となる役割を全うしました。
プレス戦術に関して言えば、
京都は前半から前線3人(原・エリアス・松田)で相手の3バックに対応する形で
プレッシャーをかけ、
横浜FCに思うようなビルドアップをさせませんでした。
中盤のインサイドハーフも連動してプレスをかけ、
横浜FCは前半はロングボールやサイド攻撃に頼る場面が多くなっています。
京都の組織的なハイプレスと中盤の構造は、
相手のミスを誘いショートカウンターを狙う意図が感じられました。
ただし後半開始直後は相手の圧力に押されてラインが下がり、
ウイングバックへの対応が遅れたため失点しました。
この点は反省材料ですが、すぐにシステム変更と選手交代で修正した点は評価できます。
セットプレーに関してはこの試合で直接得点は生まれなかったものの、
京都はコーナーキックを4本獲得し
その都度原大智や鈴木義宜といった空中戦に強い選手を狙っていました。
守備のセットプレーでも、
身長のある選手を中心にマンツーマンでルキアンらをケアし、
大きなピンチを招いていません。
GK太田も安定したキャッチングで相手のクロスを処理し、
最後の最後にビッグセーブでチームを救いました
総じて、
京都サンガのこの試合の戦術的狙いは「堅守速攻」と「柔軟なシステム運用」に集約されます。
相手の横浜FCが守備に重心を置くチームであることを踏まえ、
まずは早い時間帯にロングボールと前線の連携で先手を取るプランを成功させました。
その後も状況に応じて攻撃と守備のバランスを細かく調整し、
選手交代も的確でした。
奥川雅也という切り札的アタッカーを投入して勝ち越し点を奪った采配、
そして米本拓司や福田心之助ら守備固め要員を投入してリードを守り抜いた判断は、
チョウ・キジェ監督の手腕を示しています。
最終的に京都は2-1で逃げ切り勝利を収め、首位キープに成功しました
試合を通じてビルドアップ、プレス、セットプレー、トランジションの各局面で
狙いと修正を的確に実行できた京都サンガは、
この試合で戦術的に一枚上手だったと言えるでしょう。
これらのポイントを踏まえて映像で振り返れば、
時間経過とともに移り変わる
京都のフォーメーションと選手の役割変化が明確に理解できるはずです。

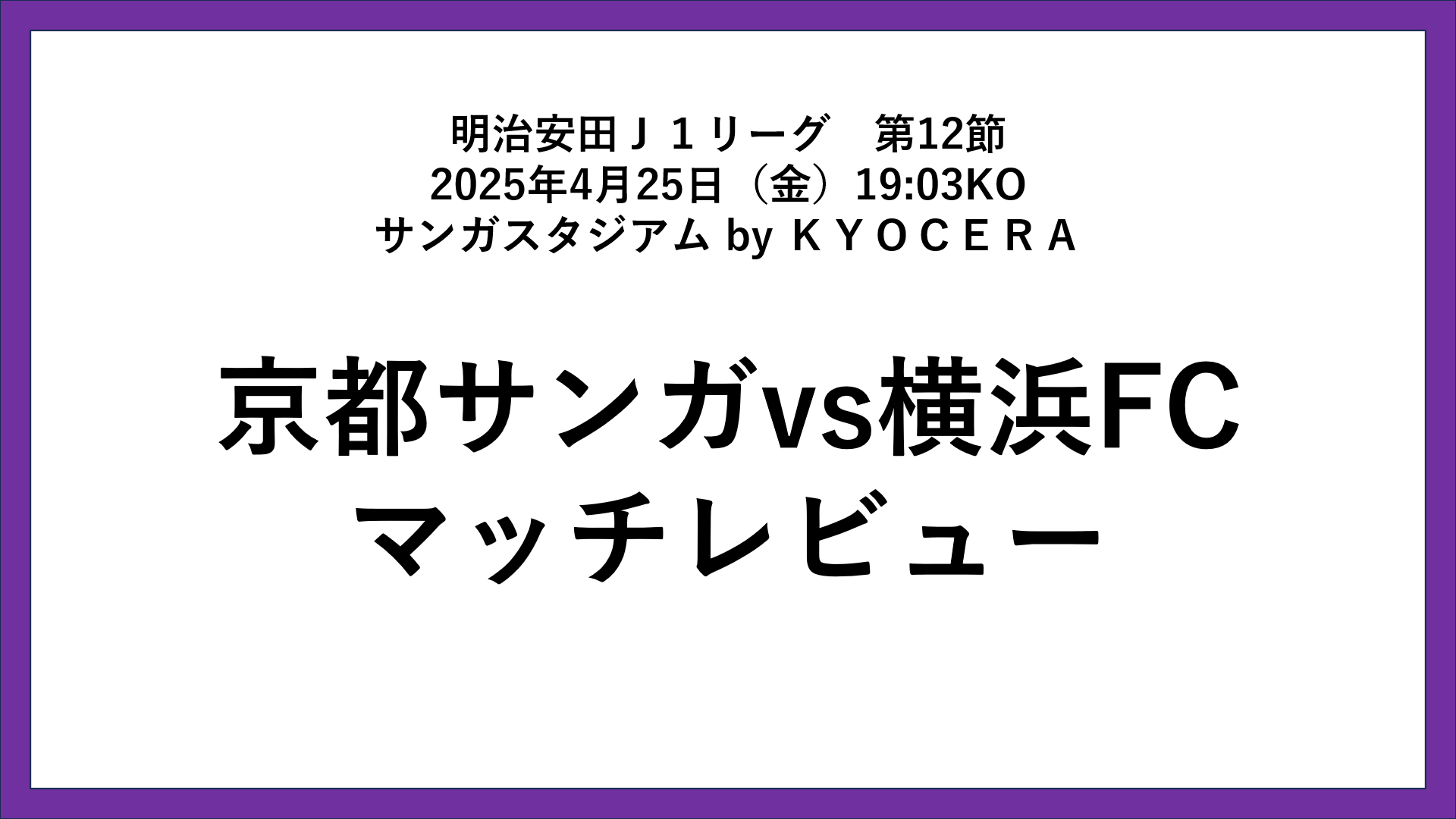


コメント