はじめに
「バーカ!」「うざい!」「言われたくねーし!」
学童保育の現場で、小学生からのきつい言葉に戸惑い、対応に悩む先生方も多いのではないでしょうか?
実際、私が学童保育で関わった小学3年生のAくんは、毎日のように「うるせーな!」「てめぇに言われたくねぇよ!」といった暴言を吐いていました。最初はショックでしたが、日々の関わりを通して彼の背景にある不安や孤独を知り、少しずつ関係を築いていくことができました。
この記事では、そういった現場での体験をもとに、口が悪くなる小学生の心理的背景と、具体的な対応方法、NG行動、信頼関係を築くためのポイントをまとめてお伝えします。
第1章:なぜ小学生は口が悪くなるのか?
◆ 心の奥にある「不安」や「甘え」
たとえばAくんは、家では親の帰りが遅く、一人で過ごす時間が長い子でした。寂しさや構ってほしい気持ちが、「乱暴な言葉で気を引く」という行動に変わっていたのです。
こうした子どもたちは「本当は先生に甘えたい、認められたい」と思っていることが多く、強がりや暴言はその裏返しでもあります。
◆ 仲間内の影響
友達との会話の中で覚えたスラングを「使ってみたい」という好奇心から口にしている場合も多いです。
実際に小学2年生のBくんは、「兄ちゃんがゲームで言ってたから」と言って暴言を真似していました。特に男子児童は、強く見せたい・なめられたくないという心理から、言葉が荒くなる傾向があります。
◆ 表現方法が未熟
「いやだった」「悲しかった」などの感情を言葉で伝えるスキルがまだ未発達な子どもたちは、「うざい」や「消えろ!」といった極端な表現を選びがちです。
言葉を整えるよりも、まず“感じたまま”を吐き出している状態です。
第2章:基本の対応方針 〜叱る前に“理解”〜
① 感情で返さない
→口調がきつくても、こちらが感情的になると悪循環になります。
ある日、Aくんに「死ねばいいじゃん」と言われ、正直ショックで言い返したくなった瞬間がありました。でも私は、深呼吸してから「それ、先生はとても悲しくなるよ」と静かに伝えました。
その後、彼はポツリと「ママにも同じこと言ったら怒られた」とつぶやき、自分の中で“言っていいこと・悪いこと”を考え始めるきっかけになったようです。
② 言葉の背景を探る
暴言の奥には、何かしらのモヤモヤが隠れています。 「学校で何かあったのかな?」「誰かとケンカしたのかな?」と声をかけることで、子どもは“気づいてもらえた”と感じます。
実際に、Bくんが「うざい!」と叫んだ日、「今日は算数で怒られた…」とぽつりと打ち明けてくれたことがありました。
③ 関係性があるからこそ言ってくる
子どもは、信頼している相手にほど、本音をぶつけてくるものです。
距離が近いからこそ、強い言葉で試す。「先生は嫌いにならない?」「突き放さない?」というテストをしているのかもしれません。
第3章:場面別対応例
◆ 暴言を吐かれたとき
- NG:「なにその言い方!やめなさい!」(感情的に怒る)
- OK:「それを聞いて先生はちょっと悲しいな。何かあった?」(気持ちに寄り添う)
ある日、Cちゃんが「うるせーんだよ、ばばあ!」と言ってきたとき、思わず言い返しそうになりました。でも私は、「Cちゃん、今日すごくイライラしてるみたいだけど、大丈夫?」と聞いてみました。
すると「ママが朝起こしてくれなくて遅刻した」と涙ながらに話してくれたのです。言葉だけ見ず、その奥を見ることが大切です。
◆ 他の子に乱暴な言葉を使ったとき
- NG:すぐに一方的に叱る
- OK:「どんな気持ちで言ったの?」「言われた子の気持ちはどうだったかな?」と一緒に考えさせる
Dくんが友達に「バカって言った」場面では、「今その言葉で、〇〇ちゃんはちょっと悲しそうな顔してたよ」とフィードバックしました。
するとDくんは、「遊びたくて言っただけ…」とポツリ。気持ちをどう伝えればいいか、練習が必要なんですね。
◆ 何度も繰り返す場合
- NG:ルール違反だけを責める
- OK:一対一でじっくり話す時間をつくる
Eくんは毎日のように暴言を吐いていたので、ある日放課後に一緒におやつを食べながら話しました。
「実は妹が生まれてから、ママが全然自分を見てくれない」とぽろっとこぼしたのです。その日から少しずつ言葉がやわらかくなっていきました。
第4章:NG対応とそのリスク
✕ 公の場で強く叱責する
→「恥をかかされた」と感じ、逆に攻撃的になることがあります。人前では感情的に叱らず、まずは距離をとって落ち着いた場所で対応を。
✕ ラベルを貼る(「口が悪い子」「問題児」)
→「どうせ自分はそういう子だから」と自己イメージが固定化し、行動改善の意欲を失わせます。
✕ 無視・黙認
→「どんなに悪口を言っても大丈夫」と誤解させることで、さらにエスカレートする危険があります。小さな暴言でもその都度“伝え方”を育てる関わりが必要です。
第5章:信頼関係を築くための工夫
◆ 普段の声かけを大切に
- 「おはよう」「今日も来てくれて嬉しいよ」など、ポジティブな声かけを積み重ねましょう。
- 毎日繰り返すことで、「この先生は自分をちゃんと見てくれている」と子どもは安心します。
◆ 「気にかけている」ことを伝える
- その場で叱らずとも、「さっきの言葉、先生少し気になってるよ。また後で話そうね」と伝えるだけで、関係が切れません。
◆ 成功体験を与える
- 簡単な係をお願いして「ありがとう、助かったよ」と伝える。
- 言葉のやり取りだけでなく、“役割”を通じて自信を育てていくことができます。
おわりに
口が悪い小学生の言葉の奥には、多くの場合「聞いてほしい」「わかってほしい」というサインがあります。
叱るより、まず理解する。
そして、子どもとの信頼関係を大切にしながら、少しずつ“伝える力”を育てていくことが、学童保育の先生にできる一番の支援です。
焦らず、根気強く、関わり続けていきましょう。
あなたの関わりが、子どもの「言葉」と「心」を育てる種になります。

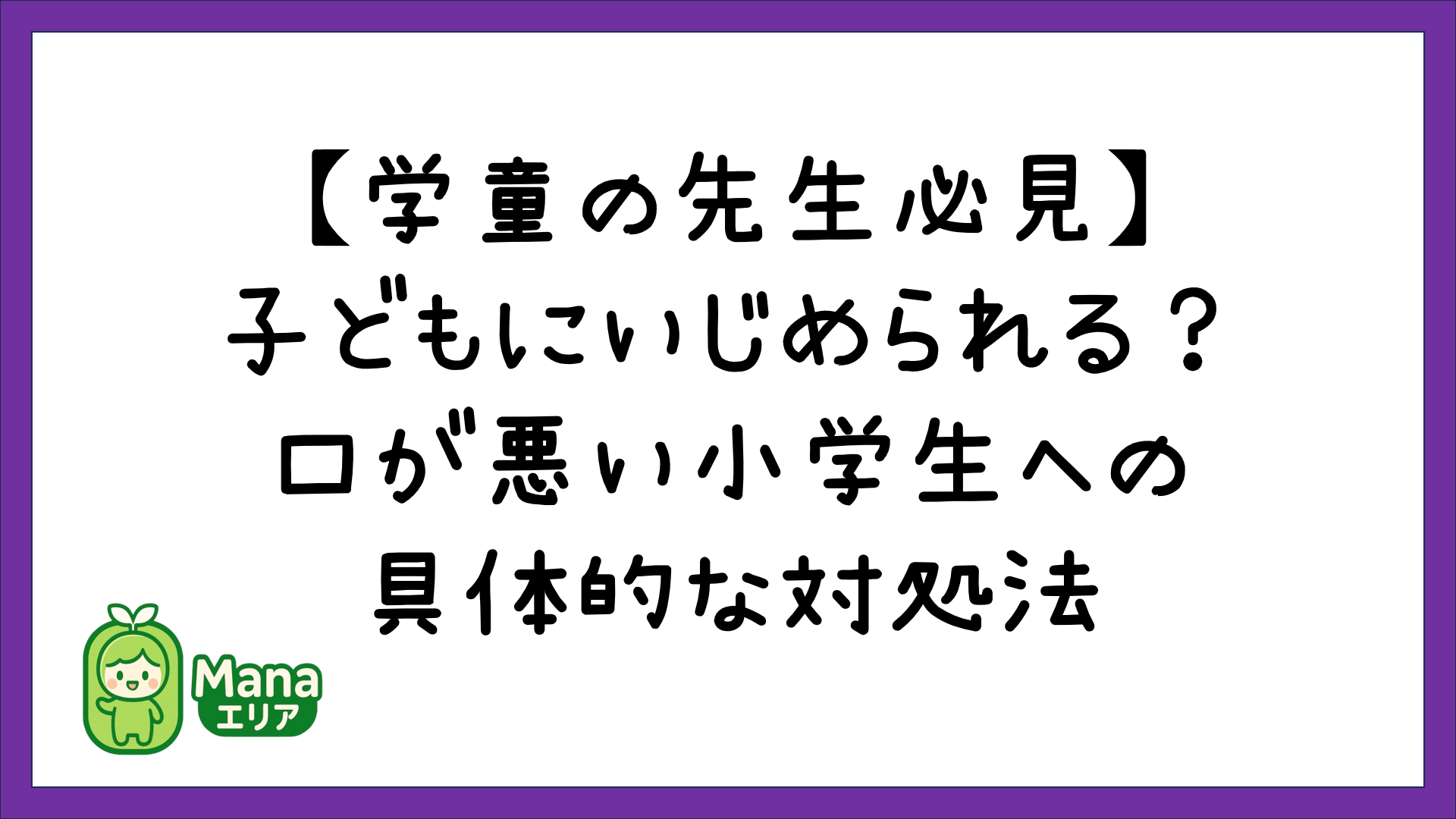
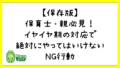

コメント