こんにちは、子育て中の親御さんに向けた記事へようこそ。 今回は、3歳から10歳くらいの子どもによく見られる「やるべきことの先延ばし」について、エピソードも交えながら、詳しくお話ししていきます。
第1章:子どもが先延ばしにするのはなぜ?
「宿題やらなさいって言ってるでしょ!」 「早く片付けて!」
そんな声、家庭でよく響いていませんか? 私も何度も言ったことがあります。しかし、子どもが動かないのには、実は“脳の仕組み”が関係していると知ってから、見方が変わりました。
脳には「前頭前野」と呼ばれる、計画や自己制御をつかさどる部分があります。この前頭前野は25歳ごろまで成長すると言われており、子どもは未発達。つまり、大人のように自分を律して行動に移すことが難しいのです。
先延ばしは「サボっている」のではなく、脳がまだ準備できていないだけなのです。
【エピソード①:9歳の息子の宿題バトル】
こんなエピソードがあります
我が家の息子は、サッカーが大好きな9歳。学校から帰ると、ランドセルを放り投げ、サッカーボールを手に外へ一直線。宿題はいつも後回し。
「宿題やったの?」「まだ…」のやりとりが日課。
でもある日、私は怒るのをやめ、「なんで宿題やりたくないの?」と聞いてみたんです。
「難しいし、失敗しそうでイヤなんだ」
この言葉にハッとしました。先延ばしの背景には、“退屈さ”“失敗の恐れ”“大変そうな気持ち”が潜んでいるのです。
第2章:先延ばしの心理的メカニズムを深掘りする
先延ばしをする原因は、脳の未発達だけではありません。
近年の研究によると、先延ばしの主な原因は次の3つです:
- 退屈さ
- 失敗への恐れ
- 課題の大きさによる心のくじけ
①「退屈さ」への脳の拒否反応
子どもは「楽しいこと」を優先します。これは単なるわがままではなく、生物学的に自然なことです。 脳は新しい刺激や達成感を求める仕組みがあり、「単調」「つまらない」と感じることからは逃れようとします。
宿題、片づけ、お手伝い……。これらは多くの場合、子どもにとってワクワクしない“作業”でしかありません。
②「失敗への恐れ」と自己肯定感の低下
子どもが「やらない」の裏にあるのは、「できなかったらどうしよう」という恐れ。
例えば、算数のプリントで過去に間違いが多かった経験があると、「また失敗する」と不安になり、避けようとする。
この“失敗を恐れる気持ち”は、自己肯定感の低下につながります。だから親は、結果よりも「やったこと」「挑戦したこと」をしっかり認めることが必要です。
③「大変そう」という曖昧な不安
大人でも、見通しの立たない仕事はつい後回しにしたくなりますよね。
子どもも同じです。「宿題を全部終わらせる」といった漠然としたゴールは、心理的に大きな壁に感じられます。
このように、先延ばしは「意志の弱さ」ではなく、脳と心の自然な反応なのです。
第3章:親ができる3つの具体的サポート
では、どうすれば子どもはやるべきことに向き合えるようになるのでしょうか?
① 課題をスモールステップに分ける
大きな課題は、小さく刻むことが大切です。
【エピソード②:小1の娘の「音読5分」チャレンジ】 娘は、音読が大の苦手。でも、学校の宿題には毎日出る。
ある日「音読全部読むの無理!」と泣き出しました。
そこで私は、こう言ってみました。 「最初の1行だけ読んでみようか」
1行読めたら、「じゃあ、もう1行だけ」。
結局、全部読めたんです。
娘は「やればできた!」と自信満々。 小さなステップが、達成感と自信に繋がった瞬間でした。
② 選ばせる・主体性を育てる
親が「これやりなさい」ではなく、選択肢を与えることで、子どもは自分の意志で動きやすくなります。
例:「先に音読する?それとも漢字ドリル?」
自分で選んだ、という感覚が、やる気につながります。
③ 達成感を“見える化”する
タスクをこなしたら、目に見える形で褒めたり、記録をつけましょう。
- チェックリストにシール
- 花丸やスタンプ
- 「がんばったねカード」を作る
【エピソード③:やる気アップカレンダー】 ある月、我が家では「宿題カレンダー」を作りました。宿題をした日はシールを1枚貼れる。
1ヶ月後、カレンダーはシールでいっぱい。 「全部貼れた!かっこいい!」と、息子は誇らしげに笑いました。
ご褒美よりも、自分の努力の“見える化”が、やる気を育てるんですね。
第4章:親自身も無理をしすぎない
ここまでいろいろお話してきましたが、親がいつも完璧に対応できるわけではありません。
私も、感情的に怒ってしまうことが何度もあります。自己嫌悪に陥る日もあります。でも大事なのは、「完璧な親」ではなく「成長していく親子」になること。
子どもができないことを責めるより、「一緒に乗り越えようね」と言える存在でありたいと、私は思っています。
第5章:まとめ 〜先延ばしは成長の一部〜
子どもがやるべきことを後回しにするのは、能力不足ではありません。脳の発達段階や心の状態に基づいた“自然な反応”なのです。
だからこそ、
- 課題を小さく分ける
- 主体性を育てる声かけ
- 達成感を見える形にする
といった具体的なサポートで、子どもの行動は少しずつ変わっていきます。
怒るのではなく、寄り添う。 無理にさせるのではなく、小さな成功体験を重ねる。
その積み重ねが、「やればできる!」という自信に変わるのです。
今日も読んでいただき、ありがとうございました。 あなたの子育てが、少しでも楽になるヒントになりますように

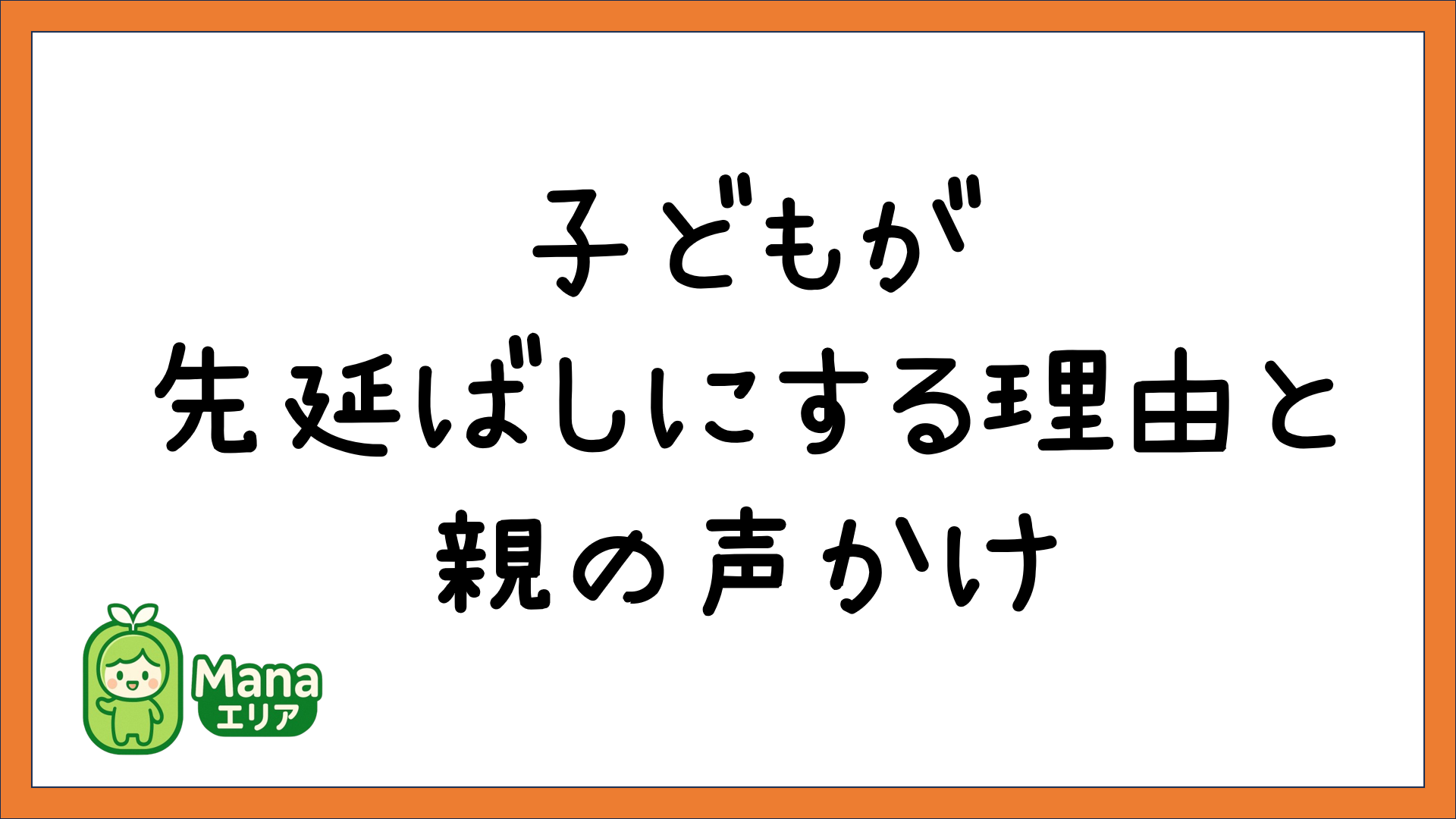
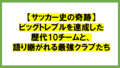
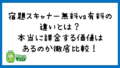
コメント